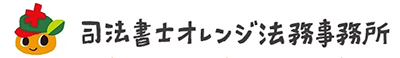自己破産とは
裁判所に申立てをして、借金を免除してもらう手続です。借金を支払う目途がまったく立たない場合に選択します。
破産に対する誤解
破産に対しては、マイナスイメージが先行し、誤解されていることが多く見受けられます。破産という制度は、今後の生活再建を目指すことを目的としたものです。決して破産者に罰を与えるような制度ではありませんのでご安心ください。
- 戸籍や住民票に破産したことが記載されることはありません。
- 選挙権がなくなることもありません。
- すべての財産を没収されるわけではありません。
- 保証人になっていない親族に借金の請求がなされることはありません。
- 一生ローンが組めなくなることはありません。
(信用情報に破産の事実が記載されるのは5~10年。) - 破産したことを理由に会社を解雇されることもありません。
自己破産のメリット・デメリット
〇メリット
・早期の生活再建が可能
借金の支払いが免除されるため、早期の生活再建が可能です。
・一定の資産は保有可能
今後の生活再建のために一定の資産(自由財産)を保有することが認められます。
・差押えをストップできる
破産手続開始決定により、給与の差し押さえを止めることができます。
×デメリット
・高価な財産は処分することに
マイホーム等の高価な物は処分する必要があります。また、その他の自由財産以外の資産も原則として処分しなければいけません
・資格制限がある
免責許可決定が確定するまでの間、生命保険募集人、宅地建物取引士、警備員など、一定の職業に就けないものがあります。
自由財産とは
自由財産とは、破産手続中でも破産者が自由に処分・使用することができる財産です。
主なものは以下の通りです。
- 99万円までの現金(預金も含む)
- 生活に必要な家財道具、衣服
- 農業従事者、漁業従事者の農業、漁業に欠くことができない器具等
なお、病気などで当分働くことができなかったり、多額の医療費等の支出が見込まれるなどの事情がある場合は、申立てまたは職権で、破産者の生活状況や収入を得る見込みなど一切の事情を考慮して、裁判所が破産管財人の意見を聞いたうえで、自由財産の範囲を拡張することもできます。
自己破産を選択する目安
借金がいくら以上というような明確な基準はなく、支払不能の状態にあることが条件となります。
支払不能の状態であるかどうかは、借金の総額の他に、財産、収入、職業などを総合的に検討したうえで、将来的にも継続して返済ができない状態かどうかを判断することになります。
自己破産の手続の流れ
1 面談の予約
面談日時の調整
面談には、事前予約が必要です。まずは当事務所にご連絡ください。
平日夜間や土日祝日しか時間が取れない方や、緊急の事態(強硬な取立行為を受けている等)があってすぐに相談したい場合も、可能な限り予定を調整して対応いたします。
面談の場所
相談の場所は、当事務所にて行っておりますが、事情により事務所までお越しいただけない方(移動手段がない方、病気や高齢のため外出が困難な方など)については、ご自宅まで出張いたしますので、お気軽にお申し付けください。
出張の場合は、一部の地域を除き、出張日当(3,300円~)をご請求させていただきます。
2 面談による相談
納得いくまで話し合い
借入の状況や内容、生活状況(家族構成、家計の収支)など、じっくりお話をおうかがいします。また、債務整理の方針についてご要望があればおうかがいします。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。
その上で、債務整理の見通し、具体的な手続きの方法、手続きの流れ、必要となる費用、依頼する際の委任契約の内容などをわかりやすくご説明いたします。ご不明な点がございましたら、納得いくまでお尋ねください。
3 債務整理の正式な依頼
委任契約の締結
相談後、ご検討していただいた上で、当事務所に債務整理を依頼される場合は、委任契約書に署名・押印をしていただきます。
着手金の支払い(分割可)
原則として委任契約締結時に報酬(着手金)をお支払していただきます。
ただし、委任契約締結後に分割払いでのお支払いもできますので、毎月の支払額・支払日については、ご相談のうえ決めさせていただきます。
お金がすぐに用意できない場合や、毎月の支払額については、依頼者の事情にあわせて柔軟に対応させていただきますので、ご安心ください。
報酬・費用については民事法律扶助制度の利用もできます
生活保護受給者や収入が一定額以下の方で、日本司法支援センター(法テラス)の定める要件を満たす場合は、報酬・費用について民事法律扶助制度をご利用いただけます。
この制度を利用した場合、法テラスが報酬・費用を無利息で立て替え、依頼者は法テラスに分割払いで返済していくことになります。詳しくは相談時にご説明させていただきます。
4 債権者へ受任通知の送付
債権者からの督促や連絡は止まります
委任契約成立後、当事務所から債権者(借入先)に受任通知を送付します。受任通知を送付することによって、その通知を受け取った債権者からの取立や連絡は止まります。その後の債権者との連絡や交渉は当事務所が一括して行うことになります。
借入先への支払いはストップします
受任通知を送付した債権者への支払いは一旦ストップします。受任通知を送付していれば、支払いをストップしても債権者から取立が来ることはありません。
また、登録貸金業者・カード会社・金融機関などから嫌がらせを受けることはありませんのでご安心ください。
5 家計の収支状況調査や手続に必要な準備
今後の生活をじっくり考える
債権者への支払いや取立行為がストップし、これまで返済や生活費のやりくりに追われて余裕のなかった精神状態から一旦解放されることになります。そこで、冷静になって、落ち着いた状態で今後の生活のことをじっくり考えてください。
家計簿をつけ、家計の収支を把握する
今後の生活のことや債務整理の方針を検討するためにも、依頼者には家計の収支を把握していただく必要があるため、受任後から家計簿をつけていただき、1カ月間の収支を表にまとめてもらいます。家計簿や収支表のつけ方については、最初にご説明させていただきますが、細かい内容ではありませんので、ご心配なさらないでください。
手続に必要な書類の準備
その他、必要な書類の収集など、依頼者の方にも手続きに必要な準備を行っていただきます。どのような準備をするのかについては、個別の事案により、チェックリスト形式の書面をお渡しいたします。
6 正確な借金総額の確定
受任通知送付後、債権者から当事務所に債権届出書(過去の取引履歴を含む)が送られてきます。通常、通知発送から2週間~1カ月程度ですべての債権者から届出があります。届出のあった債権の内容を確認して、正確な借金の総額を調査します。
7 債務整理の方針決定
現状から総合的に検討したうえで方針決定します
正確な借金総額の調査が完了した後、依頼者の家計の収支状況、財産状況等を総合的に検討した上で、最終的な債務整理の方針(任意整理、民事再生、破産)を決定します。
納得いくまで話し合うことができます。
方針の決定に関しては、依頼者の意向に沿った解決が可能かどうか、また、今後の生活のためにどのような解決を図るのが最適であるのかという観点から、司法書士と依頼者との間で十分な協議を行います。
時には、自宅を手放すかどうかという重大な決断をする場合もありますので、決して司法書士の意見を押し付けたり、結論を急かしたりすることはありません。納得いくまで検討していただけます。
事案によっては、相談の時点で、明らかに破産しか方法がないなど、最初の段階で方針が決定する場合もあります。
可能な限り依頼者の意向に沿った解決を目指しますが、条件的に不可能なご要望や違法な目的のご要望には対応できません。
8 申立の準備
まず必要な書類の収集、申立書作成に必要な事情の聞き取りを行います。破産の審理は、提出した申立書などの書面を中心に進められますので、必要書類を不足なく提出することと、事情を詳しく書面に記載する必要がありますので、きちんとした申立書を作成するには、依頼者のご協力が不可欠となります。
9 裁判所へ破産申立書を提出
住所地を管轄する地方裁判所に破産申立書を提出します。以後、裁判所からの通知・連絡等は当事務所が窓口となります。提出した申立書について、追加で提出物等が必要な場合は、裁判所から当事務所に指示があります。
10 債務者審尋のため裁判所へ出頭
債務者審尋とは
債務者審尋とは、裁判官が債務者本人と面談をして事情を聴取する手続です。最近は債務者審尋を省略する場合も多いため、必ず審尋が行われるわけではありません。
審尋が行われる場合は、申立書を提出後、裁判所から審尋ため出頭をする日時が指定されます。仕事などで都合が悪い場合は変更もできますが、必ず出頭する必要があります。
緊張する必要はありません
面談の時間は10分ほどです。提出した書類をもとに裁判官から質問がありますが、事実をありのまま答えていただけばよいので、緊張する必要はありません。また、申立書類でしっかりと事情の説明ができていれば、あまり質問されることもなく、すぐに終了します。
11 破産手続開始決定
債務者審尋の後、裁判官が支払不能の状態であると判断した場合は、破産手続開始決定が出されます。その後の手続きは財産がある場合とない場合や免責不許可事由の有無などの事情によって異なってきます。
大した財産がなく、免責不許可事由などがない場合
破産手続開始決定と同時に、手続を廃止する決定が出されます。資産の処分や配当等はしないということです。これを「同時破産廃止決定」といいます。
一定額以上の財産がある、または免責不許可事由がある場合
裁判所が破産管財人を選任して、破産者の財産や借金の経緯などの事情を調査します。財産を処分してお金に換えて、債権者に配当をおこなったり、免責を与えていいかどうかの調査が行われます。このような手続きのことを「管財事件」といいます。管財事件の場合は、裁判所から指示された額の予納金(21万円~)を裁判所に納めることになります。
12 免責の審理
同時破産廃止決定または管財事件の終結の後、裁判所が債権者に意見を述べる期間を設けます。債権者から意見が出れば、破産者は反論のために書面を提出したり、裁判所へ出頭して事情を聴かれることになります。その後、裁判所が免責を許可するかどうかの判断を行い、問題がなければ免責許可決定が出されます。
13 免責許可決定
免責が許可されると借金は免除されます
裁判所から免責許可決定が出されると、通常は1カ月ほどで確定し、手続はすべて終了します。免責許可決定の確定により、借金は免除される(支払義務がなくなる)ことになります。また、破産者ではなくなるため、資格制限のあった職業(生命保険募集人、警備員など)にも就くことができるようになります。なお、免責許可決定の確定した日から7年間は、再び破産申立てをしても、原則として免責は不許可となります。
免責後のアフターフォローもお任せください。
引越しや各種手続が必要になった場合も、最後まで親身にサポートします。
免責が認められない場合とは(免責不許可事由)
破産の審理で、裁判所が免責不許可事由に該当すると判断した場合は、原則として借金が免責されません。主な免責不許可事由は以下の通りです。
主な免責不許可事由
- 破産者が、財産を隠したり、わざと壊したり、不当に処分した等の場合
- 破産手続を遅延させる目的で、クレジットカードで商品を購入し、非常に安い値段で転売したとき
- 破たん状態にあるのに、一部の債権者だけ優遇して返済をしたとき
- 借金の原因が浪費やギャンブルによるものであるとき
- 破産申立の1年前から破産手続開始決定あった日までの間に、破たん状態であるのにウソをついて、信用取引によって借入れをしたとき
- 事業の帳簿などを隠したり、偽造や変造したとき
- 裁判所にウソの報告をしたとき。
- 破産管財人等の職務を妨害したとき
- 過去7年以内に、次の事由があったとき
-
- 破産の免責決定が確定していた
-
- 給与所得者再生の再生計画の履行があった
-
- 再生計画の履行が困難になった場合の免責決定が確定していた
- 破産法に定められた破産者の義務に違反したとき
裁量免責とは
免責不許可事由に該当した場合でも、破産に至った経緯や、その他の事情を考慮して、裁判官の裁量で免責を許可することが妥当であると判断したときは免責が認められます。
破産の実務では、浪費やギャンブルで借金をしたケースなどであっても、最終的には裁量免責により、免責が許可されることが多々あります。
裁量免責の前提として、破産管財人を選任して事情の調査や経過観察をしたり、積立てをして債権者に配当をするように命じられることもありますが、最終的にはほぼ免責が認められます。
免責不許可事由に該当しそうな場合でも、あきらめずにご相談ください。
破産しても免責されない債権とは
破産申立をして、免責許可決定があっても免責されない債権があります。 主なものは以下の通りです。
- 租税等の請求権(国税、地方税、社会保険料など)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(詐欺や横領での損 害賠償など)
- 破産者が故意または重大な過失で加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(人を殴ってけがをさせた場合や、重大な不注意で 起こした交通事故でけがを負わせた場合の損害賠償など)
- 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生じる費用の分担義務、子の監護に関する義務、親族間の扶養義務、および以上の義務に類する契約に基づく義務に係る請求権(養育費など)
- 従業員への給料や預り金
- 破産者がわざと債権者名簿に記載しなかった債権
- 罰金等
債務整理によくある質問
Q破産申立から免責決定までの期間は?
通常は、同時破産廃止決定の場合で約3~4カ月ほどです。管財事件の場合は、案件ごとに異なります。
Qマイホームがある場合の破産手続きは?
原則として破産管財人が処分することになります。売却するまでに時間はかかりますので、すぐに家を明け渡さないといけないわけではなく、十分引越し等の準備をする時間はありますのでご安心ください。また、引越し先の手配のために信頼できる不動産業者をご紹介することもできますので、ご相談ください。
お問い合わせはこちら(TEL/LINE/E-mail)
費用
着手金 220,000円
管財事件の場合は297,000円