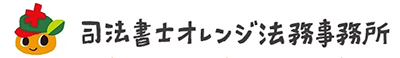個人再生とは
裁判所に申立てをして、借金総額の一部(最低弁済額)を3~5年の分割払いで支払うことにより、残りの借金を免除してもらう手続です。
マイホームを維持しながら支払える
住宅ローンがある場合は、マイホームを手放すことなく、住宅ローンの支払いを続けながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。(ただし、住宅ローンは一切減額されません。)マイホームを手放したくないけど、住宅ローン以外に多額の借金があるという方に最適の手続きです。
例)住宅ローン以外の借金が総額500万円ある場合、住宅ローンはそのまま支払いながら、住宅ローン以外の借金について、総額100万円(小規模個人再生の場合)を3年間の分割払いで支払い終えれば(月額27,778円)、残りの借金はすべて免除されます。
個人再生のメリット
- マイホームの維持が可能
住宅ローンはそのまま支払い、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるため、マイホームを手放さずに済みます。
- 余裕を持った生活再建が可能
手続の受任から再生計画に基づく支払いを開始するまで約1年程度の期間を要するため、その間に今後の支払いに向けた積み立てをするなど、余裕をもった準備ができます。
- 借入金の使途(支払不能に至った原因)は問われない
借入金の使途は問われないため、破産の場合は免責不許可事由にあたるギャンブルや遊興費のために借金が膨らんだ場合でも問題なく認可決定を受けることができます。
- 資格の欠格事由にならない
保険の外交員、宅地建物取引士、警備員など、破産の場合は、破産開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、資格制限を受けるものがありますが、個人再生には資格制限はありません。
個人再生のデメリット
- 資産が多いと利用しにくい
保有する資産の総額が多い場合、最低弁済額が高額になるため利用しにくくなります。
- 信用情報機関に完済から5年間は記録が残る
個人再生をすると、信用情報機関に完済から5年間は事故情報が残るため、その期間内に新たに借入の申し込みをした場合は、審査が通らず、借入ができない場合があります。
(審査の基準は各カード会社、金融機関等で異なります。)
個人再生申立の要件
- サラリーマン、自営業者などの個人であること。
- 将来において継続反復して収入が見込まれること。
- 借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローン特則利用の場合は住宅ローンは除く)
最低弁済額
小規模個人再生の場合
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
| 100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上 1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上 3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円を超え 5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
| ※住宅ローン特則利用の場合は住宅ローンを除く | |
保有資産の総額が最低弁済額を超える場合
保有する資産の総額が上記最低弁済額を超える場合は、その資産額以上を弁済しなければなりません。たとえば、上記の規定では最低弁済額が100万円となる場合でも、所有する自動車や生命保険の解約返戻金などの資産価値の総額が150万円あった場合は、最低弁済額は150万円となります。
弁済期間
原則3年間。特別な事情がある場合は、裁判所が認めれば最長5年まで延長できます。
個人再生手続の流れ
1 面談の予約
面談日時の調整
面談には、事前予約が必要です。まずは当事務所にお電話ください。
受付時間 年中無休 9:00~19:00
平日夜間や土日祝日しか時間が取れない方や、緊急の事態(強硬な取立行為を受けている等)があってすぐに相談したい場合も、可能な限り予定を調整して対応いたします。
面談の場所
相談の場所は、当事務所にて行っておりますが、事情により事務所までお越しいただけない方(移動手段がない方、病気や高齢のため外出が困難な方など)については、ご自宅まで出張いたしますので、お気軽にお申し付けください。
出張の場合は、一部の地域を除き、出張日当(3,300円~)をご請求させていただきます。
2 面談による相談
納得いくまで話し合い
借入の状況や内容、生活状況(家族構成、家計の収支)など、じっくりお話をおうかがいします。また、債務整理の方針についてご要望があればおうかがいします。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。
その上で、債務整理の見通し、具体的な手続きの方法、手続きの流れ、必要となる費用、依頼する際の委任契約の内容などをわかりやすくご説明いたします。ご不明な点がございましたら、納得いくまでお尋ねください。
3 債務整理の正式な依頼
委任契約の締結
相談後、ご検討していただいた上で、当事務所に債務整理を依頼される場合は、委任契約書に署名・押印をしていただきます。
着手金の支払い
個人再生着手金(税込)※分割可
小規模個人再生 275,000円
給与所得者再生 330,000円
住宅ローン特則利用の個人再生 385,000円
原則として委任契約締結時に報酬(着手金)をお支払していただきます。ただし、委任契約締結後に分割払いでのお支払いもできますので、毎月の支払額・支払日については、ご相談のうえ決めさせていただきます。
お金がすぐに用意できない場合や、毎月の支払額については、依頼者の事情にあわせて柔軟に対応させていただきますので、ご安心ください。
報酬・費用については民事法律扶助制度の利用もできます
生活保護受給者や収入が一定額以下の方で、日本司法支援センター(法テラス)の定める要件を満たす場合は、報酬・費用について民事法律扶助制度をご利用いただけます。
この制度を利用した場合、法テラスが報酬・費用を無利息で立て替え、依頼者は法テラスに分割払いで返済していくことになります。詳しくは相談時にご説明させていただきます。
4 債権者へ受任通知の送付
債権者からの督促や連絡は止まります
委任契約成立後、当事務所から債権者(借入先)に受任通知を送付します。受任通知を送付することによって、その通知を受け取った債権者からの取立や連絡は止まります。その後の債権者との連絡や交渉は当事務所が一括して行うことになります。
借入先への支払いはストップします(住宅ローンは支払継続)
受任通知を送付した債権者への支払いは一旦ストップします。受任通知を送付していれば、支払いをストップしても債権者から取立が来ることはありません。
また、登録貸金業者・カード会社・金融機関などから嫌がらせを受けることはありませんのでご安心ください。住宅ローン特則利用の場合は、住宅ローンの支払いは継続し、滞納があれば解消するようにします。
5 家計の収支状況調査や手続に必要な準備
今後の生活をじっくり考える
債権者への支払いや取立行為がストップし、これまで返済や生活費のやりくりに追われて余裕のなかった精神状態から一旦解放されることになります。
そこで、冷静になって、落ち着いた状態で今後の生活のことをじっくり考えてください。
家計簿をつけ、家計の収支を把握する
今後の生活のことや債務整理の方針を検討するためにも、依頼者には家計の収支を把握していただく必要があるため、受任後から家計簿をつけていただき、1カ月間の収支を表にまとめてもらいます。
家計簿や収支表のつけ方については、最初にご説明させていただきますが、細かい内容ではありませんので、ご心配なさらないでください。
手続に必要な書類の準備
その他、必要な書類の収集など、依頼者の方にも手続きに必要な準備を行っていただきます。どのような準備をするのかについては、個別の事案により、チェックリスト形式の書面をお渡しいたします。
6 正確な借金総額の確定
受任通知送付後、債権者から当事務所に債権届出書(過去の取引履歴を含む)が送られてきます。通常、通知発送から2週間~1カ月程度ですべての債権者から届出があります。届出のあった債権の内容を確認して、正確な借金の総額を調査します。
7 債務整理の方針決定
現状から総合的に検討したうえで方針決定します
正確な借金総額の調査が完了した後、依頼者の家計の収支状況、財産状況等を総合的に検討した上で、最終的な債務整理の方針(任意整理、民事再生、破産)を決定します。
納得いくまで話し合うことができます。
方針の決定に関しては、依頼者の意向に沿った解決が可能かどうか、また、今後の生活のためにどのような解決を図るのが最適であるのかという観点から、司法書士と依頼者との間で十分な協議を行います。
時には、自宅を手放すかどうかという重大な決断をする場合もありますので、決して司法書士の意見を押し付けたり、結論を急かしたりすることはありません。納得いくまで検討していただけます。
事案によっては、相談の時点で、明らかに破産しか方法がないなど、最初の段階で方針が決定する場合もあります。
可能な限り依頼者の意向に沿った解決を目指しますが、条件的に不可能なご要望や違法な目的のご要望には対応できません。
8 申立の準備
依頼者には、受任後から家計簿をきちんとつけてもらい、1か月分を収支表にまとめてもらいます。そして毎月1回、当事務所にて面談を行い、収支状況のチェックや申立てに向けた打ち合わせを行います。これを最低3か月間行います(個人再生申立には直近3か月分の家計収支表を添付する必要があります)。
また、依頼者には申立ての準備のため、必要書類の収集を行ってもらいます。
9 裁判所へ申立
準備が整い次第、住所地を管轄する地方裁判所に書面を提出して個人再生手続開始の申立てを行います。申立後、裁判所との連絡や郵便物の受領等はすべて当事務所で行います。
10 開始決定、弁済金の積立て
申立後、書類の補正などがあれば対応し、裁判所から個人再生手続開始決定が出されます。このとき、裁判所から依頼者に対して、積立ての指示があります。
積立てとは、依頼者が再生計画の通りに支払いができるかどうかを判断するために、毎月の弁済額に相当する金額を3カ月間積立てさせるものです。実際は申立前から積立を開始します。
積立額の目安としては、再生計画の毎月の弁済額が28,000円ほどになる場合は、積立額は3万円程度になります。依頼者には、裁判所に指示された通り、毎月積立てをしてもらいます。
11 再生計画認可決定
小規模個人再生の場合は、債権者の書面による決議が行われ、再生計画案に反対する債権者が半数に満たず、かつ、その債権額が負債総額の2分の1を超えないときは、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
12 再生計画に基づいて支払いを開始
再生計画認可決定が確定した月の翌月から支払いをスタートします。支払方法は債権者の指定する預金口座に依頼者から直接振り込んでもらいます。
完済するまで債権者との連絡は当事務所が行います
入金の管理はすべて依頼者ご本人に行ってもらいますが、完済するまでは当事務所と依頼者との委任契約は継続しますので、債権者や裁判所との連絡は当事務所が行います。
支払いができなくなりそうな場合など、何かあれば当事務所にご連絡ください。
13 完済
完済した場合は、債権者から借用書等契約書類が当事務所に返還されますので、返還があり次第、依頼者にお渡しいたします。
完済後のアフターフォローもお任せください。
何か困ったことがあればご相談ください。最後まで親身にサポートいたします。
個人再生によくある質問
Q1 初回の支払日はいつになる?
順調に手続きが進んだ場合の目安は、手続の受任から裁判所への申立てまで最短でも3カ月はかかります。さらに、裁判所へ申立をしてから再生計画に基づく支払いを開始するまで6~8カ月ほどかかります。
Q2 税金の滞納がある場合は?
滞納している税金や国民健康保険料などの租税公課については、個人再生手続を申立てても一切減免されません。したがって、個人再生手続とは別に、納付先の担当者と支払方法の協議を行って、全額支払う必要があります。
Q3 再生計画どおりの支払いができなくなった場合は?
再生計画の変更
やむを得ない事由で再生計画に基づく支払いが著しく困難となった場合には、裁判所に再生計画の変更を申し立てることができます。やむを得ない事由とは、たとえば、勤務先の業績が悪化してボーナスが出なくなったり、給料が大幅に減らされた場合などがあてはまります。
変更後の支払期限は、再生計画で定められた最終の期限から2年を超えない範囲で定めなければなりません。当初の返済期間が3年であった場合は、再生計画認可時から起算して5年まで延長することができます。
ハードシップ免責
以下の要件をすべて満たしている場合は、裁判所に申立てをして残りの債務を免除をしてもらうことができます。これをハードシップ免責と言います。
ハードシップ免責の要件
- 再生債務者がその責めに帰すことができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難になったこと。
- 再生計画で定められた弁済総額のうち、その4分の3以上の弁済を終えていること。
- 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
- 再生計画の変更をしても、支払いを続けるのが極めて困難であること。
破産申立に移行
再生計画の変更もハードシップ免責も受けることもできない場合は、自己破産申立の手続に移行するしかありません。
Q4 住宅ローンがあと数年で完済になる場合でも利用できる?
住宅ローンの残高が、その住宅の土地建物の価値を下回る場合は、差額分が資産として扱われるため、最低弁済額が多くなり、個人再生を選択することが難しい場合があります。
例)
①住宅ローンの残高が600万円
②自宅の土地・建物の評価額が合計1000万円の場合
土地・建物の資産価値(①-②)は400万円になります。
他に何も資産がなかったとしても、保有する資産額以上は弁済をしなければならないため、最低弁済額は400万円以上となります。これを3年間で支払うと月額11万円ほどになります。